
本記事の内容
- プロンプトエンジニアリングの講座を受講するメリット
- プロンプトエンジニアリングを学べるおすすめ無料講座
- プロンプトエンジニアリングを学べるおすすめ有料講座
本記事の執筆者

うぃる(@willblog13)
この記事を書いているぼくも、TechAcademyの「はじめてのプロンプトエンジニアリングコース」という講座を受講して、勉強を始めました。
そんなぼくが、プロンプトエンジニアリングを学ぶのに最適な講座を「無料」「有料」に分けて紹介していきますね。
ちなみに、ぼくは講座の受講は"必須"と考えてます。
なので、実際に有料講座を受講したぼく目線で、講座を利用するメリットも紹介していきます。ぜひ判断材料にしてください。
それでは、早速いきましょう。
-

はじめてのプロンプトエンジニアリングコースの体験レビュー【TechAcademy】
続きを見る
プロンプトエンジニアリングの講座を受講するメリット
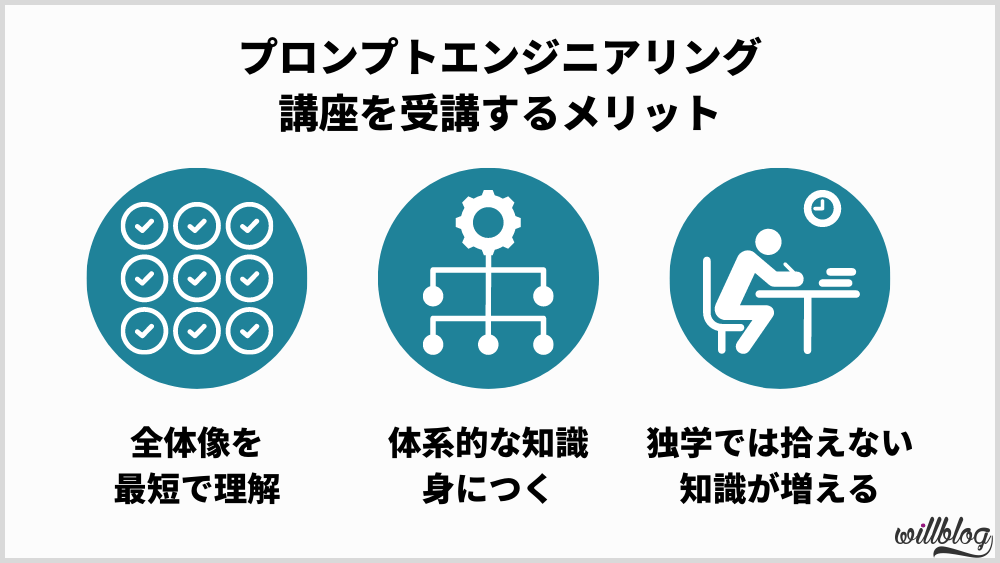
まずは、プロンプトエンジニアリングの講座を受講するメリットを解説していきます。それが以下のとおり。
- 全体像を最短で理解できる
- 体系的な知識が身につく
- 独学では拾えない知識が増える
それぞれ深掘りしていきます。
全体像を最短で理解できる
1つ目のメリットが「プロンプトエンジニアリングの全体像を最短で理解できる」ことです。
やっぱり論文やブログ記事で学習しても断片的な知識しか身につかないんですよね。
けど、講座で体系的に学べば、その心配はありません。
講座を活用して、以下の順番で学ぶのがおすすめです。
- オンライン講座でプロンプトエンジニアリングの全体像を理解する
- 本や論文、ブログ記事などで知識を補完していく
遠回りをしないためにも、オンライン講座から始めてみましょう。
体系的な知識が身につく
2つ目のメリットが「体系的な知識が身につく」ことです。
先ほども述べたように、論文やブログ記事だと体系的には学習できないですよね。
しかし、オンライン講座は初心者が理解しやすいように、プロが教材を作成しています。
その分費用はかかりますが、投資する価値は十分にあります。
もし「イマイチ理解しづらいな」と悩んでいる人は、思い切って講座を受講することをおすすめします。
独学では拾えない知識が増える
最後3つ目のメリットが「独学では拾えない知識が増える」ことです。
実際、ぼくもTechAcademyの講座を受講したときに感じました。
たとえば、
- AIの歴史
- ChatGPT APIの使い方
- トークンと確率分布の関係性
などは、独学では触れられなかったであろう知識です。
こんな風に新たな発見がある意味でも講座を受講する価値ありです。
-

はじめてのプロンプトエンジニアリングコースの体験レビュー【TechAcademy】
続きを見る
プロンプトエンジニアリングを学べるおすすめ無料講座

プロンプトエンジニアリングを学べるおすすめの無料講座が以下のとおりです。
- Prompt Engineering Guide
- Learn Prompting
- ChatGPT Prompt Engineering for Developers
それぞれの特徴やどんなところがおすすめなのかをご紹介します。
Prompt Engineering Guide
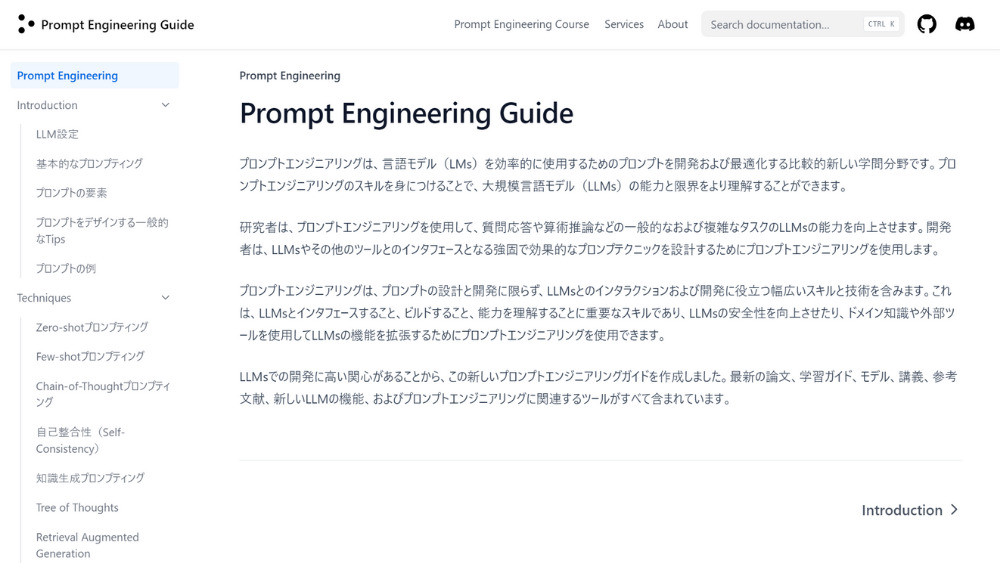
プロンプトエンジニアリングをはじめから学ぶなら、「Prompt Engineering Guide」です。
AIの研究、教育、技術の民主化を目指す海外コミュニティ「DAIR.AI」が作成しており、
プロンプトエンジニアリング界隈でも「教科書」的な扱いを受けています。
学べる内容
- プロンプトエンジニアリングの基礎
- ChatGPTなどに活用できるプロンプト設計
- 主要なAIモデルの紹介
- AIやプロンプトのリスク
- プロンプトエンジニアリングの論文集
以前は英語版だけでしたが、日本語版もついにリリース。日本の方でも違和感なく学べますよ。
プロンプトエンジニアリングの基本を身につけたいなら、このサイトからどうぞ。
» Prompt Engineering Guide(日本語版)はコチラ
» Prompt Engineering Guide(英語版)はコチラ
Learn Prompting
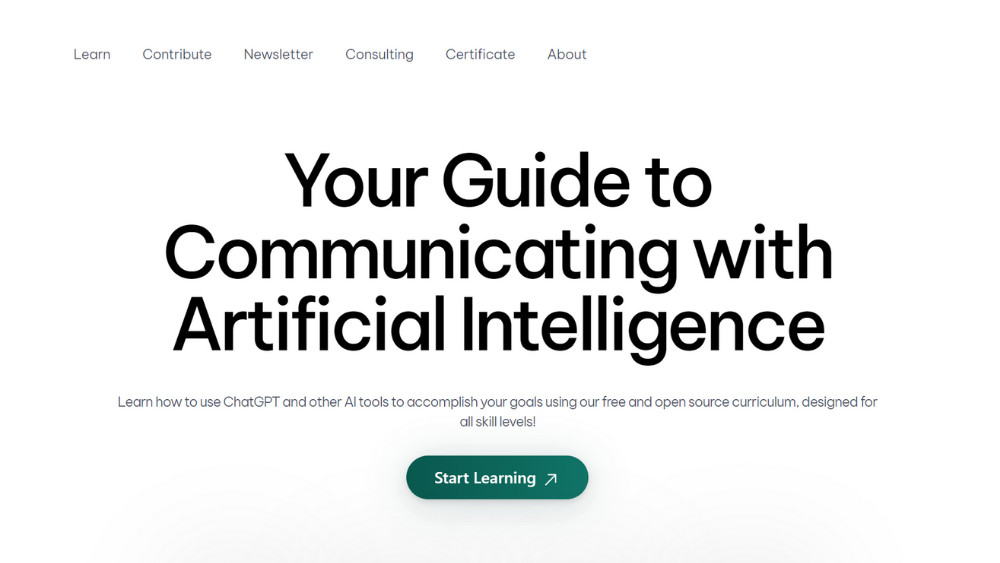
Learn Promptingは、先に紹介したPrompt Engineering Guideを噛み砕いたような講座です。
とはいえ、やさしいだけでなく上級者向けの情報も揃っているのが良い点。
学べる内容
- プロンプトエンジニアリングの基礎
- 中級者向けのプロンプトエンジニアリング技術
- 上級者向けのプロンプトエンジニアリング技術
- プロンプトに関するリスクや対策
- 最新のAIツール
情報量はダントツかと。しかも分かりやすくまとめているので、とても勉強になります。
とはいえ、一部コンテンツは英語のみになっています。DeepLなどで訳しながら勉強しましょう。
ChatGPT Prompt Engineering for Developers
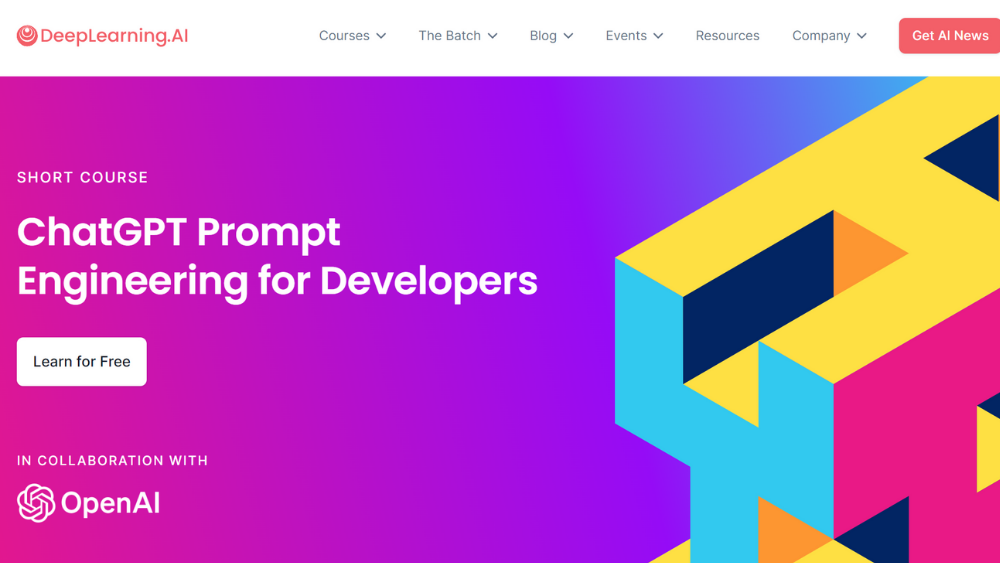
ChatGPT Prompt Engineering for Developersは、OpenAIとDeepLearning.AIによる開発者向けコンテンツ。
期間限定で無料公開されています。
学べる内容
- プロンプトの書き方
- 条件分岐に関する知識
- その他プロンプトエンジニアリングの知識(ChatGPTベース)
主に開発者向けの内容ですが、初心者にも役立つ内容が書かれています。
すべて英語です。Google翻訳やDeepLなどで翻訳しながら読み進めていきましょう。
» ChatGPT Prompt Engineering for Developers(Learn for Free)
プロンプトエンジニアリングを学べるおすすめ有料講座

プロンプトエンジニアリングを学べるおすすめの有料講座が以下のとおりです。
- はじめてのプロンプトエンジニアリングコース by TechAcademy
- プロンプトエンジニアリング入門講座 by パイソンメイカー
- Udemyのプロンプトエンジニアリング各種講座
それぞれの特徴やどんなところがおすすめなのか、どんな点が無料講座と違うのかをまとめていきますね。
はじめてのプロンプトエンジニアリングコース by TechAcademy

| 講座名 | はじめてのプロンプトエンジニアリングコース |
| 運営スクール | Tech Academy |
| 期間 | 4週間 |
| 費用 | 149,600円 |
特徴
- 基本はテキスト学習
- ケーススタディが豊富
- メンターに気軽に質問できる
- 課題があるため実践力が身につく
- メンターから課題のレビューや回答をもらえる
TechAcademyといえば、大手のプログラミングスクール。
そんなTechAcademyが新たにリリースしたプロンプトエンジニアリングの入門向けコースです。
特に非エンジニアの方に向けた講座になっています。
ちなみに、ぼくもTechAcademyの「はじめてのプロンプトエンジニアリングコース」を受講しました。
レビュー記事はこちら
-

はじめてのプロンプトエンジニアリングコースの体験レビュー【TechAcademy】
続きを見る
プロンプトエンジニアリング入門講座 by パイソンメイカー

| 講座名 | プロンプトエンジニアリング入門講座 |
| 運営スクール | パイソンメーカー |
| 期間 | 月額制 |
| 費用 | 22,000円 |
特徴
- AIとPython活用を重視した講座
- ChatGPTの活用を学べる
- AI開発に必須のPythonの基礎から応用まで学べる
- 最適なプロンプト設計とその事例を学べる
- 講義は週に1回60分
ChatGPTを活用したい方はもちろん、AI開発に必須のPythonを学びたい方にも適したコースです。
週1回の講義なので、比較的ゆったりとしたペースで進められるのもいいところですね。
ちなみに、ホリエモンの「ChatGPT大全」という本を予約購入すると、当講座の初月料金が499円になります。22,000円→499円はヤバすぎですね。。。
Udemyのプロンプトエンジニアリング各種講座

| 講座名 | Udemyのプロンプトエンジニアリング各種講座 |
| 運営スクール | Udemy |
| 期間 | なし |
| 費用 | 1,800~21,800円 |
必要に応じて、Udemyのプロンプトエンジニアリング関係の講座も受講してみましょう。
Udemyとは、学習教材のオンラインマーケットプレイス。質の高い講座・情報が手に入ることで有名です。
- ChatGPTの使い方
- ChatGPT×Excel VBAのプロンプトエンジニアリング
- 大規模言語モデル(LLM)のアプリケーション開発
上記のように、各講座によってテーマが異なるので、自分にあった講座を見つけましょう。
元々は海外のサイトなので、海外の講座のほうが良質なものを発見しやすいです。
まとめ:講座はプロンプトエンジニアリング学ぶ最短ルート
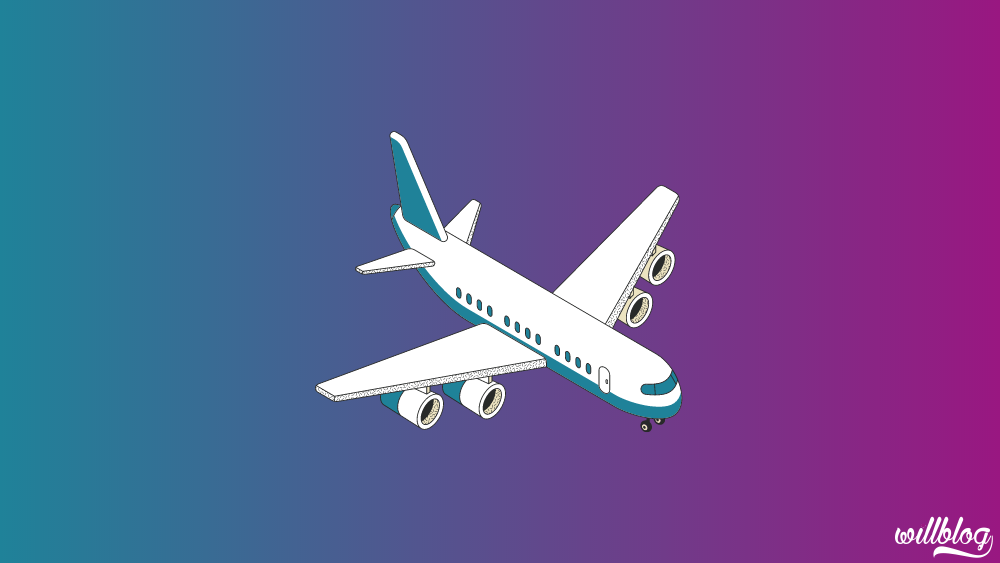
- 最初はオンライン講座で学び始めるのがおすすめ
- 講座体系的な知識が身につく
- 講座がプロンプトエンジニアリング学習の最短ルート
繰り返しになりますが、これから本格的にプロンプトエンジニアリングを学んでいきたい人は、ぜひ講座を受講してみてください。
特に有料講座はメンターのサポートも含まれるので、分からないことがあればすぐに聞くことができます。
レビュー記事を下記に貼っておきます。参考にしてください。
-

はじめてのプロンプトエンジニアリングコースの体験レビュー【TechAcademy】
続きを見る
それでは、また。

