■大学院生向けコミュニティを立ち上げました!【無料】
「大学院生になったけど、将来が不安…」と悩んでいませんか?当コミュニティは、就活情報、自力で稼ぐための情報、その他の有益な知識を共有しあう初の院生特化コミュニティ。「もっと視野を広げたい」と考えている大学院生の方はぜひ参加してみてください。
下記から無料で参加できます。
» 無料の大学院生コミュニティに参加する
※案内のための公式LINEに飛びます。

本記事の内容
本記事の執筆者

うぃる(@willblog13)
この記事を書いているぼくは、2022年3月に大学院を修了して、現在はとある東京の大企業で働いています。
研究室の人間関係ってちょっと特殊ですよね。
ぼくも最初はその特殊な人間関係に戸惑いがありました。
しかし、ぼく自身は最終的に教授・同期・先輩・後輩のすべてと上手に関われたと自負しています。
なので、ぼくの体験談も踏まえつつ、研究室の人間関係について解説していきます。
記事を読めば、研究室の人間関係を改善するヒントを得れますよ。
あわせて読みたい
-

【厳選】自己分析ツールのおすすめ7選【登録なし/無料あり】
続きを見る
研究室の人間関係がうまくいかない理由
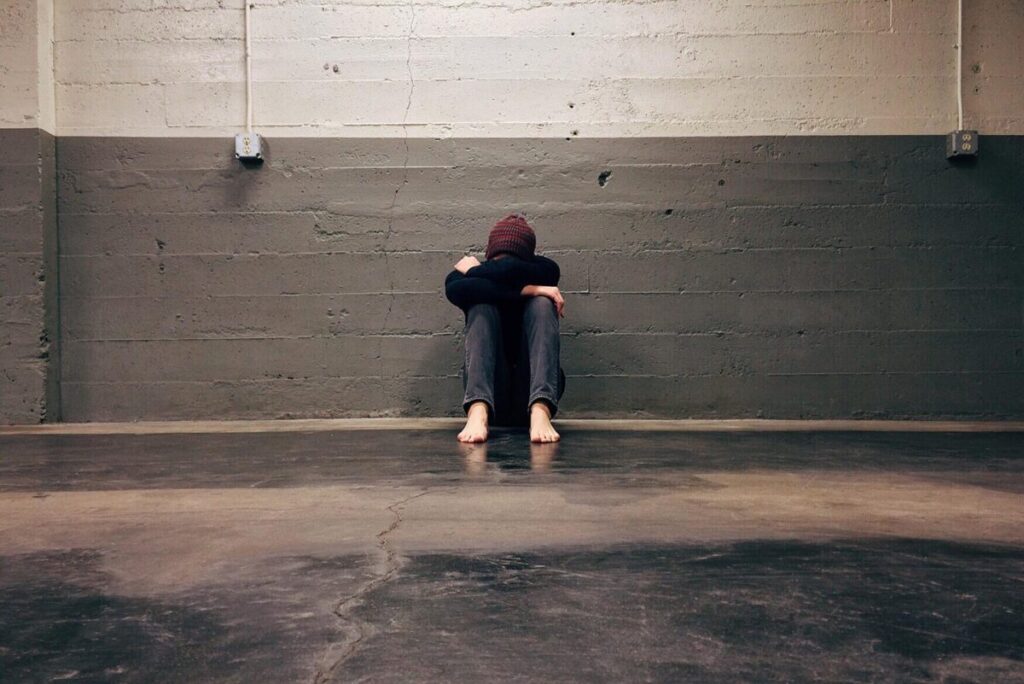
はじめに、なぜ研究室の人間関係がうまくいかないのか、その理由を見ていきましょう。
考えられる理由を3つ厳選しました。
- メンバーのバランス感が悪いため
- 明確なリーダーがいないため
- お互いに研究や就活へのストレスを抱えているため
それぞれ解説していきます。
メンバーのバランス感が悪いため
1つ目の理由は「メンバーのバランスが悪いため」です。
顕著なのが男女比かなと思います。
特に理系の研究室だと余計男が多くなってしまいますよね。
男女比が偏ると、少数派は過ごしにくくなってストレスが溜まりますよね。
ぼくの研究室でも全体の9割が男だったので、1割の女性陣はちょっと過ごしにくくしてたかなと思います。反省。
場合によっては、メンバーのバランス感の悪さが人間関係をこじれさせるきっかけになってしまうのかなと思います。
明確なリーダーがいないため
2つ目は、「明確なリーダーがいないため」です。
明確なリーダーがいないと、誰が指示するのか、誰が取りまとめるのかが毎回ばらばらになってしまい、人間関係がうまくいかなくなってしまいます。
例えば、部活動とかだと部長、サークルとかだとサークル長といったように明確なリーダーがいますよね。
そのリーダーが全体を見ていることで、人間関係のいざこざは極力減らすことができます。
一方で、研究室の実質リーダーは教授。
しかし、教授は生徒の人間関係にはあまり介入してこないですよね。
その結果、研究室内の生徒において、明確なリーダーがいなくなってしまうため、統率が取りにくくなってしまいます。
お互いに研究や就活へのストレスを抱えているため
3つ目が「お互いに研究や就活へのストレスを抱えているため」です。
自分が研究や就活へストレスを抱えているのはわかると思いますが、当然相手側も同じようなストレスを抱えています。
そして、ストレスを抱えた者同士はぶつかりやすい、、、。
ぼくも就活真っ最中のときに、できるだけ同期と関わらないようにしていました。
明確な理由はないのですが、「この状態で話したらうまくいかなそう」という危険察知があったのだと思います。
人によってはストレスをコントロールできなくて他人にあたったりする人もいます。
そんな人を避ける方法を次の項目で解説していきますね。
あわせて読みたい
-
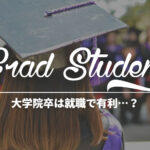
大学院卒は就職において有利?【学部卒との違いも解説】
続きを見る
研究室の人間関係が辛いときの対処法

続いて、研究室の人間関係で苦しんでいる人向けの内容です。
研究室の人間関係が辛いときの対処法をまとめました。
- 自分なりに息抜きをする
- 極力リモートで研究する
- 他の研究室または他大学院に移る
上から実行しやすい順になっています。
基本的には「逃げろ」ということに集約されますが、それぞれ簡単に説明しますね。
①自分なりに息抜きをする
まずは軽度の人向け。「研究室の人間関係めんどくさいなあ~」くらいの人。
そういう方はまず自分なりの息抜きをしましょう。
- 映画を観る
- 読書をする
- 旅行に行く
- スポーツをする
- ボーッとする
なんでもOKです。いわゆる自分の好きなこと・趣味ですね。
読書したい方はコチラ
-

読書をすれば「圧倒的な自己成長」ができる理由【人生イージー】
続きを見る
旅してみたい方はコチラ
「いや、研究がどうしても忙しいんだけど、、、」
という方は、ぜひ次を見てください。
②極力リモートで研究する
「研究が忙しい、だけど研究室に行きたくない」という方にオススメなのが、「極力リモートで研究する」ということです。
今の時代、リモートでもある程度仕事できたり、研究できたりってことがわかってきましたよね。
ぼくも研究室時代は8割リモートでやっていました。
なお、研究のテーマによっては毎日研究室に行って実験を行わないといけない、という方もいると思います。
そういった方は、実験だけ集中的に研究室でやり、それ以外のことは家に帰ってからやるなど、工夫を考えましょう。
③他の研究室または他大学院に移る
最後、本当に研究室の人間関係が辛いと思っている人向けです。
それが他の研究室や他大学院に移るという選択です。
主に学部生でこれから進学を検討している人向けですね。
ぶっちゃけめんどくさい先輩・教授がいるという場合は、どうしようもないんですよね。
何か自分が行動しても、その人たちがいなくなる確率は低いので。
なので、自分から逃げちゃうのが一番の最適解になると思います。
「いや、もう自分修士なんだけど・・・」
っていう方もいるかなと思いますが、別の場所に移動するのは諦めましょう。
それよりは、①、②を駆使しながらさっさと研究室生活を終えた方が得策です。大学院卒は就職において有利?【就活を制する方法も解説】で解説するとおり、大学院だと就活も楽ですしね。
なにはともあれ、できるだけ苦手な人から距離を置くことに全力を注ぎましょう。
-

大学院を辞めたいと思った時の対処法ロードマップ4STEP【我慢ダメ】
続きを見る
相手別にみる研究室の人間関係をよくする行動

最後は、研究室の人間関係で苦しんでいるわけではないが、より良くしたいと思っている人向けの話です。
やっぱり研究室では同期・先輩・後輩・教授と様々な人たちを相手にしなければなりません。
なので、それぞれに対して、どのような関わり方をすればいいのかをぼく目線で解説していきます。
研究室の同期との人間関係
はじめに、研究室の同期ですね。
同期は一番近い存在。
だからこそ、大切にすべきですよね。
ぼくも一人だけ同期がいましたが、就活や研究など辛いときはお互いに励まし合っていました。
同期は貴重な存在なので、変にぶつからず味方にするように心がけるのがベストだと思います。
研究室の先輩との人間関係
続いては、研究室の先輩との人間関係です。
先輩は研究から就活までいろいろなアドバイスをくれる存在です。
特にぼくが重視するのは、就活における先輩の存在です。
やっぱり先輩は就活を乗り越えているわけですから、ノウハウを持っているんですよね。
大学院卒は就職について解説した記事では特に触れなかったのですが、先輩から就活の情報をもらえるのは大学院生の特権かもしれませんね。
研究室の後輩との人間関係
次は、研究室の後輩ですね。
ぶっちゃけ研究室の後輩に関しては、そんなに重視する必要はないかなと思います。
仲良くしたいなら仲良くすればいいし、みたいな感じです。
なお、大掛かりな調査や実験をする際は後輩たちに手伝ってもらうことは多々あります。
なので、そういったときに助けてもらえるように日頃から友好な関係を結んでおくのは大事だと思います。
研究室の教授との人間関係
最後に、研究室の教授との人間関係。
一番重要です。
なぜなら、研究室に関しては教授が一番偉いから。嫌われたら終わり。
研究においても就活においても、教授が何も動いてくれないとかなりきつい思いをすると思います。
ぼくに関しては、教授とかなり友好な関係を築けていたので、逆に研究も就活も円滑に進めることができました。
研究室と就職って関係あるの?の記事でも書いたとおり、教授の存在は就活において特に重要。
変に歯向かったりせずに仲良くやっておきましょう笑
-
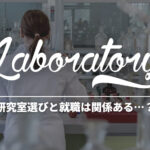
研究室選びと就職は関係ある?失敗しないための選び方を紹介
続きを見る
それでは、また。
あわせて読みたい
-

【無料】大学院生向け就活サイトのおすすめ12選【注意点あり】
続きを見る
