
本記事の内容
本記事の執筆者

うぃる(@willblog13)
年間300冊のペースで本を読むブロガーである私が、「全部読まない」読書術のやり方について書いていきます。
また、本記事の内容は、ぼくが読んだ10冊以上の「読書術」の本で、必ずと行っていいほど共通していた内容です。
なので、本記事の信頼性=10冊以上の有識な「読書術」の本となります。
結論、最強の速読法は「全部読まないこと」です。
本記事では、その「全部読まない」読書術のやり方について紹介します。
この記事を読めば、「全部読まない」読書術のやり方を理解でき、本1冊を早く読めるようになりますよ。
「全部読まない」が本を早く読む最適の方法です
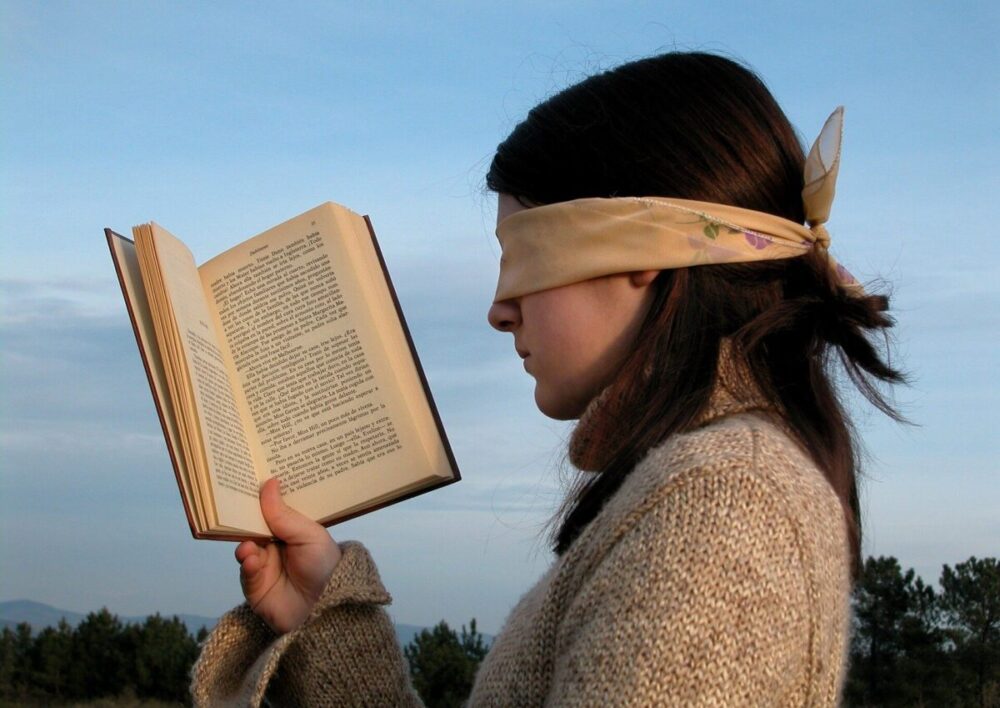
繰り返しにはなりますが、本は「全部読まない」ことが重要です。
「全部読まない」は様々な読書術の本で共通して推められている方法です。
参考にした書籍
-

【2023年最新】読書術のおすすめ本10選と今すぐにできる読書術
続きを見る
「全部読まない」読書術と義務教育の落とし穴
ぶっちゃけ、この方法に違和感を持つ人も多いはず。
なぜなら、皆さんは娯楽しての読書が身についてしまっているからです。
皆さんは小説やエッセイなどの娯楽としての読書を身につけてしまっているため、本を1ページ目から全部読もうとしがちです。
ていうか、そもそも日本の義務教育的にもそのような読み方を教わりますよね。
実際、ぼく自身も今回紹介する方法を知るまではそうでした。
そんなことを繰り返していました。
たしかに小説などストーリーがあるものは最初から読まないと意味がわからなくなってしまいますもんね。
すっ飛ばして読んでいたら「え!?こいつが犯人なん!?」など不測の事態が起こることも・・・。
しかし、ビジネス書、実用書ではぶっちゃけ途中から読んでも全く問題はありません。
小説ではタブーな「犯人を先に見る」ようなことを先にやってもOK。
なので、自己成長のための本に関しては「結論を先に見ちゃいけない」という固定観念を忘れるようにしましょう。 続きを見る

読書をすれば「圧倒的な自己成長」ができる理由【人生イージー】
「全部読まない」読書術のメリット
- 時間短縮につながる
- 心理的ハードルが低くなる
- 記憶への定着が良い
当然ですが、全部読む場合に比べて、自分が読みたい部分を読んでいるだけなので時間がかかりません。
さらに、1冊読むことへの心理的ハードルがぐっと低くなり、読書習慣をつけやすくなります。
なぜなら、「全部読まなくていいんだ!」「1冊読むのに時間がかからないんだ!」といった意識が生まれるからです。
さらにさらにメリットとして、記憶の定着が良いことが挙げられます。
皆さんも経験があると思いますが、1冊本を読み切ったあとにその本の内容を思い出すとしても、全然説明ができないことありますよね。
実際「全部読む」で得られるものは1冊読み切ったという「達成感」だけ。
一方で、「全部読まない」では、得る情報が厳選されているかつ、自分の知りたい部分を読んでいるので、記憶に残りやすい。
全部読んで頭に残らないのと、情報を厳選して記憶に残るのでは圧倒的に後者のほうが良いですよね。
ということで、以下では実際に「全部読まない」方法を紹介していきます!
「全部読まない」読書術のやり方手順
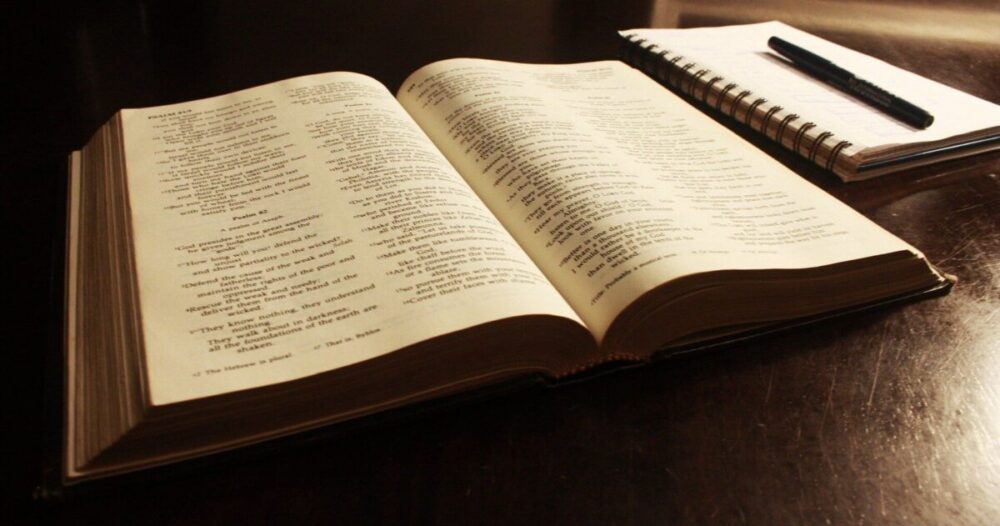
- 本の表紙、帯、まえがき、あとがき、目次から本の全体像を把握し、内容を予測する
- 読む前にその本から何を得たいのかを明確にする
- 目次を見て読むところと読まないところを明確にする
- 「速読」か「精読」かを決める
- 知りたい部分だけを読む
「全部読まない」読書術のやり方1:事前準備
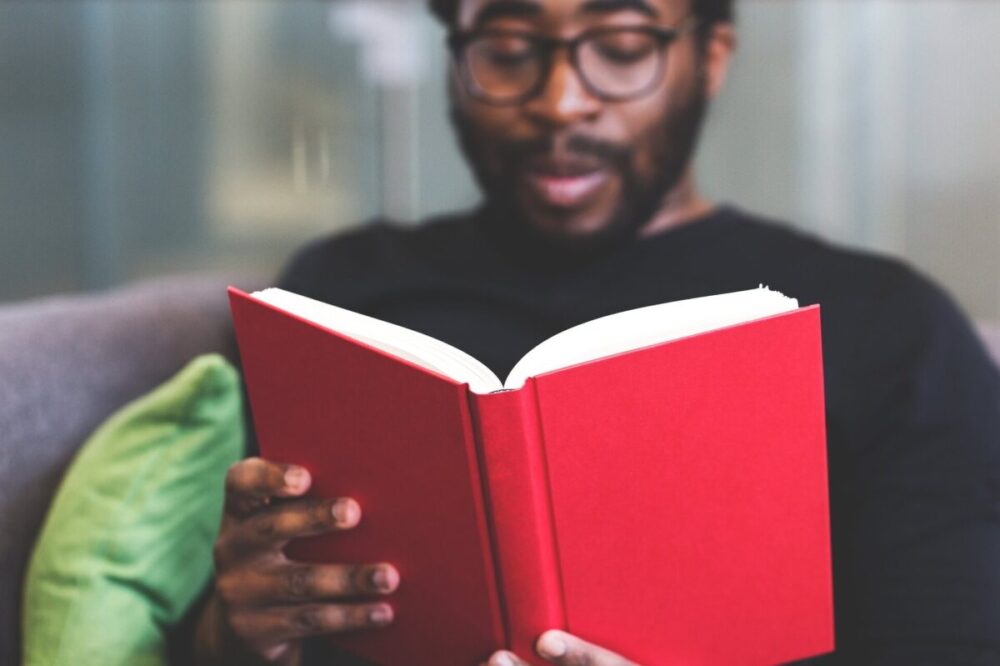
step
1本の表紙、帯、まえがき、あとがき、目次から本の全体像を把握し、内容を予測する
最も重要な作業です。
小説読みに慣れている人はいきなり1ページ目から読み進めようとしがち。
しかし、ビジネス書・実用書ではまず、全体を把握しましょう。
その全体把握に使えるのが「表紙」「帯」「まえがき」「あとがき」「目次」です。
例えば、今回記事を作る上で参考にした一つである「東大読書」の表紙・帯には下記のような言葉が書いてあります。
- 「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく 東大読書 現役東大生 西岡壱誠
- 勉強にも仕事にも効く!「こんな読み方、あったんだ」
- 真似するだけで、誰でも、どんな本でも! 早く読める 内容を忘れない 応用できる
- 偏差値35から奇跡の合格を果たした現役東大生の読書法!
- 一生使える、5つの「スゴい読み方」
- 「読み込む力」を劇的に上げる・・・仮説読み
- 「論理の流れ」がクリアに見える・・・取材読み
- 「一言で説明する力」を鍛える・・・整理読み
- 「多面的なモノの見方」を身につける・・・検証読み
- 「ずっと覚えている」ことができる・・・議論読み
- 「今、あなたが読むべき本」の探し方も解説
↓↓↓↓↓
- ただの読書術ではなさそう。頭を良くするような読書術が書いてあるんだろうな。
- 筆者は現役の東大生。
- 筆者はこの読書法で偏差値を爆上げしたんだろうな。
- この読書法を実践すると早く読めるようになりそう。
- この読書法を実践すると本の内容が定着しやすくなりそう。
- この本では5つの読書法を紹介しているんだな。
- この読書法を実践すると「読み込む力」「論理の流れ」「一言で説明する力」「多面的なモノの見方」「ずっと覚えている」が身につくんだな。
- 選書の方法も書いているな。
このように、表紙と帯だけでこれだけの情報を掴むことができます。
それと同時に、この本にはこんな事が書いてあるんだろうなという予測も立てることができます。
これにプラスしてまえがき・あとがき・目次を読み込めば、この本の全体像の把握は完璧ですね
このステップをまとめると、本の「出発地」と「ルート」を把握しましょうということです。
step
2読む前にその本から何を得たいのかを明確にする
全体把握が終わったら、その本から何を得たいのかを明確にしてください。
先程紹介した「東大読書」を例に上げてみましょう。
そして、その目的によって読むべきところも変わってきます。
読書術だけを知りたい人が、選書方法の章を読み込んでも頭に入らないですよね。
要するに、ここでは本の「目的地」を把握しているということです。
「全部読まない」読書術のやり方2:スキニング
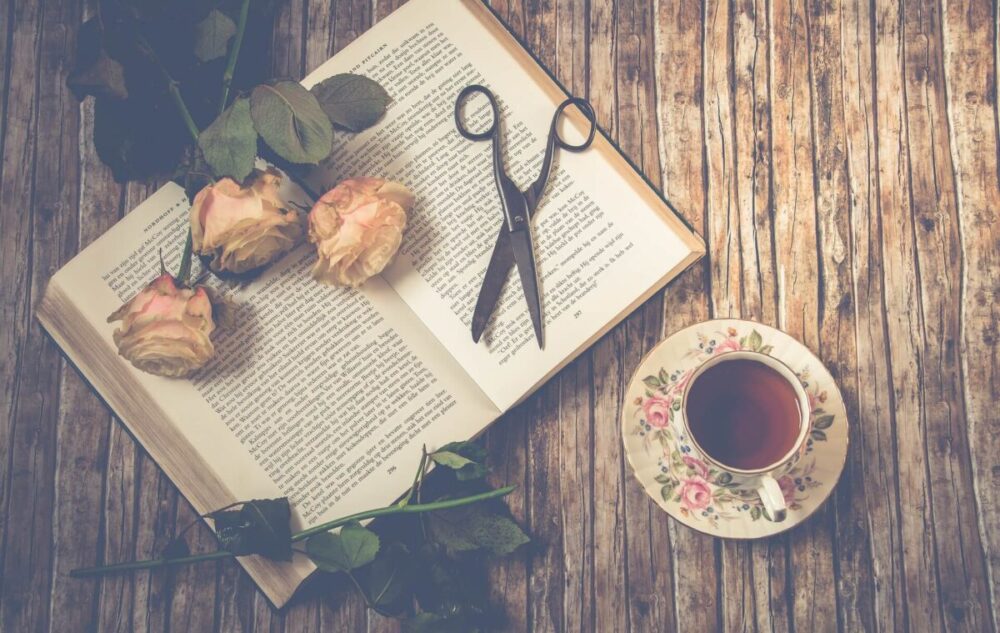
まず、はじめに説明すると「スキニング」とは「拾い読み」のことです。
つまり、必要な箇所だけ集中して読む「全部読まない」ことを指します。
step
3目次を見て読むところと読まないところを明確にする
さて、「出発地」「ルート」「目的地」が分かったところで、どのルートをすっ飛ばすかを決めていきます。
そこで有効なのが目次です。
先程明確にした「その本から何を得たいのか」と目次を照らし合わせ、自分が読むべきところを厳選します。
ここで重要なのが、思い切りですね。
本当に自分の目的にフィットした部分だけ読むように心がけましょう。
step
4「速読」か「精読」かを決める
「出発地」「ルート」「目的地」「どこをすっ飛ばすか」を決めたら、読みたい箇所の「手段」を決めましょう。
目次を見て本当に理解したいところは「精読」。
その「精読」をするために必要だけど、本当に知りたいところではない部分を「速読」とするのが良いでしょう。
「全部読まない」読書術のやり方3:読む
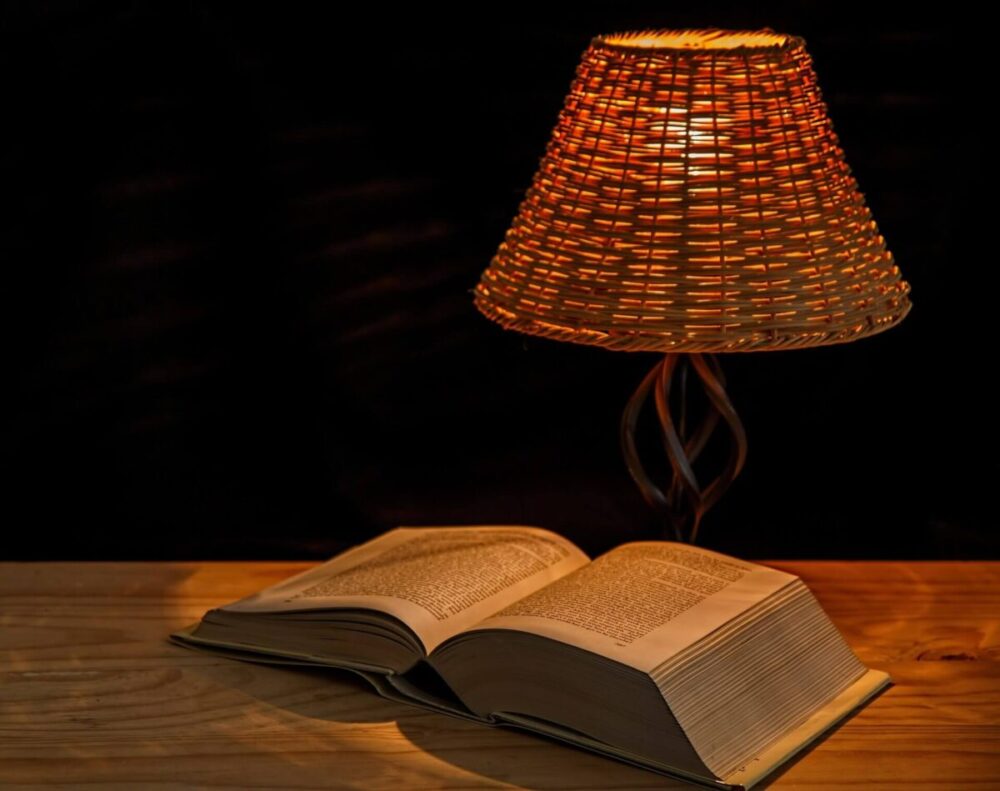
step
5知りたい部分だけを読む
あとはSTEP①~③で決めた読むべき箇所をSTEP④で決めた読み方で読むだけ。
もちろん目次ですべてがわかるわけではないので、読んでいて「あんまり自分の知りたいことと関係なかったな」と思う箇所も出てくるはず。
そうした場合も読まないようにするなど、「読みながらスキニング」もしてみてください。
参考にした書籍
-

【2023年最新】読書術のおすすめ本10選と今すぐにできる読書術
続きを見る
【読書術】「全部読まない」が本を早く読む最適の方法ですのまとめ

- 「全部読まない」メリットは「時間短縮・心理的ハードル低下・記憶定着」
- 本を読む前には「出発地」「ルート」「目的地」を把握することが重要
- スキニングには思い切りが大事
いかがでしたか。
結構長文を書いてしまいましたが、「辞書のように読む」という捉え方が一番わかりやすいですかね。
と同じように、自分の知りたい情報・知識を、目次から探して、その部分だけ読む。
まずは、これと同じ要領で気軽に本を読んでみるのをおすすめします。
ぜひトライしてみてください! 続きを見る 続きを見る
それでは、また。

読書術マスターまでの完全マップ【入門~上級まで:全15記事で解説】

ビジネス書が読み放題のサービス7選を比較【おすすめの選び方も解説】
