
本記事の内容
本記事の執筆者

うぃる(@willblog13)
年間300冊のペースで本を読むブロガーである私が、複数回読みという効果的な読書術について書いていきます。
ぼく自身、10冊以上の読書術に関する本を読みました。
その中でも信頼性が高く効果がある情報から記事を書いています。
結論、本の内容を忘れないための読書術は「複数回読む」です。
正しくは「1回の時間を短縮して、複数回読む」という方法。
今回はこの読書術について解説していきます!
この記事を読めば、複数回読みのやり方を理解でき、本の内容を定着させることができるようにになりますよ。
本の内容を忘れない読書術は「複数回読み」です
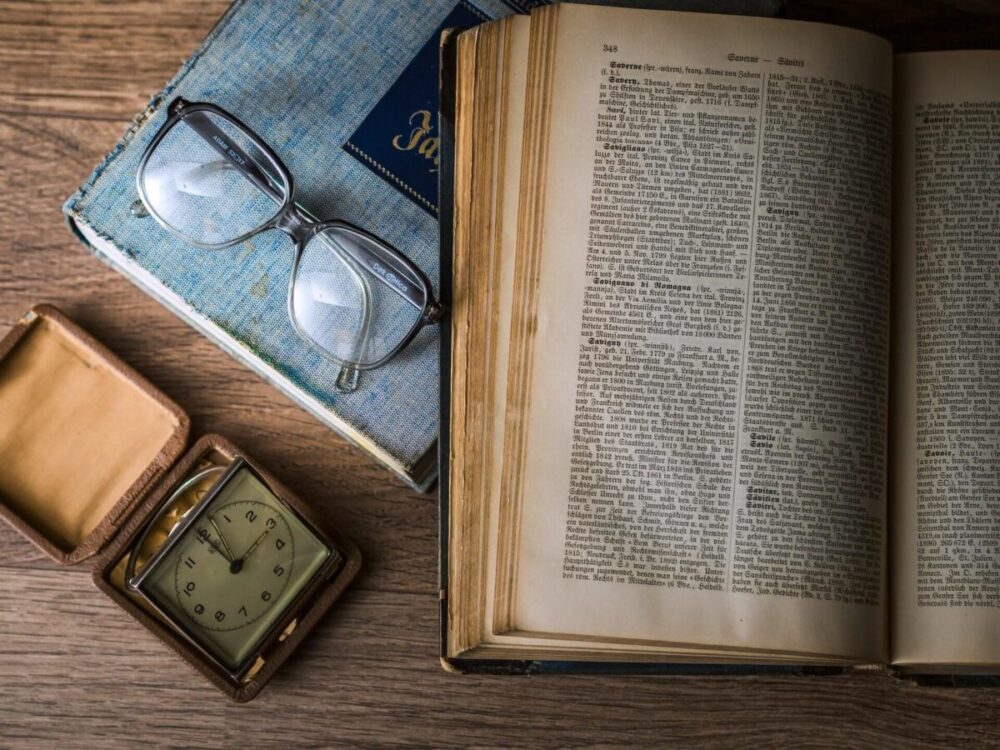

冒頭でも述べたように、本の内容を忘れないためには「1回の読書時間を超短縮した複数回読み」が有効です。
複数回読みの意味
まず、はじめに「複数回読み」の部分。
後述もしますが、人間の脳は反復することによって記憶の定着を図っています。
なので、読書にしても内容を頭に入れたければ複数回読むのが効果的なのです。
しかし、ここで問題になってくるのが「複数回読む=時間、労力がかかる」といった点ですよね。
「1回の読書時間を超短縮した」の意味
そこで、次に「1回の読書時間を超短縮した」の部分。
複数回読むことのよってかかる時間を非常に短くします。
と思うかもしれません。
しかし、速読法は身につける必要はなく、ポイントを抑えて読めば、速読と同じ速さかつ、速読よりも記憶の定着がよくなります。
その方法に関しては下記の記事で紹介しています。
-

【読書術】「全部読まない」が本を早く読む最適の方法です【速読】
続きを見る
このように時間短縮×複数回読みによって超効率的かつ超記憶定着が良い最強の読書をすることができるのです。
本の内容を忘れない読書術「複数回読み」のメリット
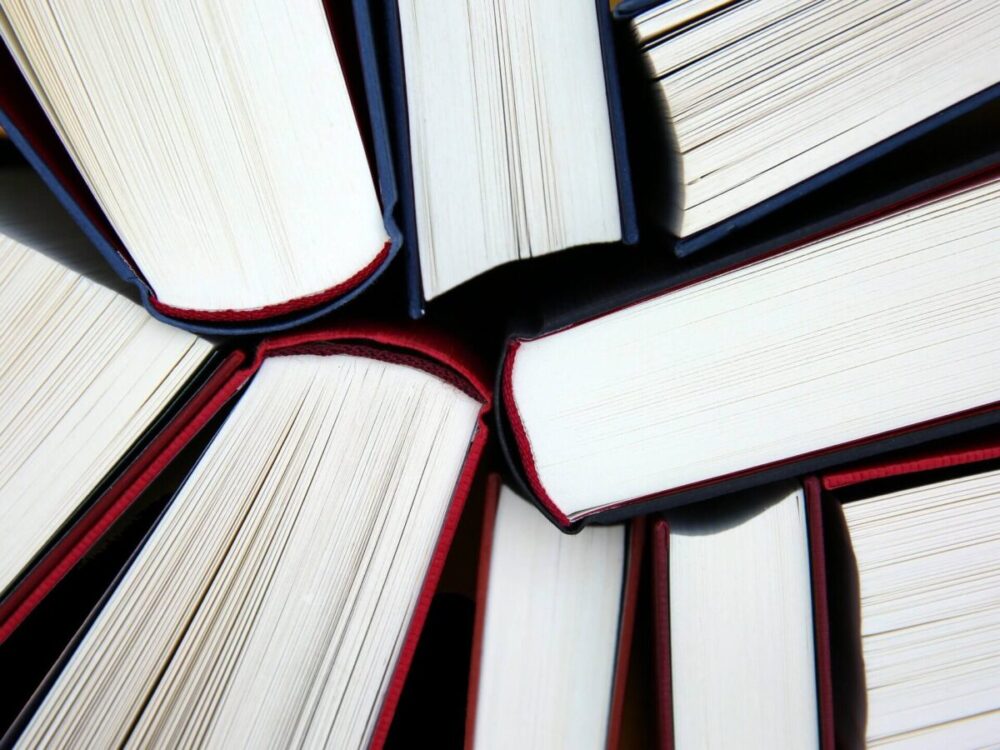
メリット
- 記憶への定着が良い
- スキマ時間を有効活用できる
- 読書への心理的ハードルが下がる
①記憶へ定着が良い
人間というのは反復することによって記憶に残るようになります。
よく英単語を覚えるときも何回も繰り返し、読み書きをしますよね。
あれと同じです。
複数回読みは普通の読書に比べて記憶への定着が良くなります。
しかし、読書になると皆さん「本は1回読んで理解できる」と思い込んでいます。
なので、「本は1回じゃ理解できない、何回も読むことで理解できるようになるんだ」というマインドを持ちましょう。 続きを見る

【克服】本の内容が理解できない原因とその対処法を徹底解説
②スキマ時間を有効活用できる
今回紹介する複数回読みでは、1回の読書の時間を極限まで短くしてそれを複数回くり返すということを行います。
なので、1回のかかる読書時間は非常に短いため、通勤電車、休憩中、入浴中など、様々なスキマ時間を利用して読書を続けることができます。
何事も習慣づけるにはスキマ時間の有効活用は必須ですよね。 続きを見る

【多忙なあなたへ】読書時間の作り方おすすめ5選【具体例あり】
③読書への心理的ハードルが下がる
先程も述べたように複数回読みでは1回の読書時間が短いので、疲れません。
複数回読みによって読書の習慣もつきやすくなります。 続きを見る

読書を習慣化する方法5選を紹介【年間100冊読めた】
本の内容を忘れない読書術「複数回読み」のやり方手順

本記事では複数回といっていますが、本によってその回数はまちまちです。
なので、3回の場合と7回の場合それぞれ分けて簡単に手順を解説します。
「複数回読み」のやり方手順①:3回読み
- 1回目:重要だと思う点をドッグイヤー(15分程度)
- 2回目:ドッグイヤーしたところとその前後だけ読む(10分程度)
- 3回目:自分の行動にどう活かせるかを考える(5分程度)
1回目
まず1回目に関しては重要点をざっと洗い出し、気になるページにドッグイヤーをしてください。
ドッグイヤーとは本の端を折り曲げるあの行為のこと言います。
ドッグイヤーに関してもっと詳しく知りたいかたは下記から。 続きを見る

【脱付箋】本にドッグイヤーをつける意味とメリットを解説
2回目
次に、2回目はドッグイヤーしたところとその前後だけ読み、自分の知りたい情報を抜き出します。
「本の全部読まなくてよい」これを念頭に置きましょう。
3回目
最後に、3回目では自分の行動への活かし方を意識しながら読み推めます。
つまり、アウトプット前提で読み進めるということです。
ちなみに、上記の時間目安は、本で述べられていたタイムをそのまま書き出しました。
これらは、個人個人で自分にあった時間を見つけ出してください。
「複数回読み」のやり方手順②:7回読み
- 1回目:見出しの把握
- 2回目:アウトラインの把握1回目
- 3回目:アウトラインの把握2回目
- 4回目:キーワードの把握1回目
- 5回目:キーワードの把握2回目
- 6回目:説明文把握(精読)
- 7回目:最終確認&補填
見出しの把握
見出しの把握を行うことで、本にどんな事が書いてあるのかを大まかに把握します。
見出しの把握とは表紙、帯、目次等を読むことを指します。
アウトライン
ここでは、実際に本をパラパラとめくり、見出しや太字部分を読むことでこの本での重要な点をざっと洗い出します。
キーワードの把握
ここでは、ここまでくるとある程度本のあらすじは理解できているはずなので、この本が主張する点を明確に理解するためにキーワードに注目します。
キーワードは特に文章中に何回も出てくる単語、太字になっている単語等に着目すると良いでしょう。
説明文把握
説明文把握とは、つまり精読を行うということ。
ここまでである程度内容が頭に入っているはずなので、自分が気になるところ、理解できなかったところを重点的に見ていきます。
普通の精読は文章を読みながら、アウトラインやキーワードを把握したりしないといけないのですが、複数回読みではそれが必要なく、精読に集中することができます。
最終確認
最後に、最終確認です。
改めて脳に焼き付けたいところやちょっと理解ができていないところを補充します。
7回読みに関してはもっと詳しく知りたい方は下記の記事を参考にしてください。 続きを見る
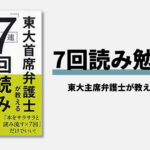
【東大主席弁護士】7回読み勉強法のやり方を紹介【内容・感想・書評】
「本の内容を忘れない読書術は「複数回読み」」のまとめ

- 最強の読書術は「1回の読書時間を超短縮した複数回読み」
- 「本は1回じゃ理解できない、何回も読むことで理解できるようになるんだ」というマインドを持とう
- 複数回読みは「3回読み」か「7回読み」がおすすめ
いかがでしたか。
今回紹介した「1回の読書時間を超短縮した複数回読み」が最も合理的な読書術かと思います。
読書の習慣をつけようとして挫折した経験がある人はたくさんいるはず。
しかし、「本は1回じゃ理解できないのだから気楽に読もう」というマインドを持ってから読書習慣が身につきました。
皆さん、ぜひこの読書術を実践して良い読書ライフを!
それでは、また。 続きを見る 続きを見る

読書術マスターまでの完全マップ【入門~上級まで:全15記事で解説】

ビジネス書が読み放題のサービス7選を比較【おすすめの選び方も解説】
