■大学院生向けコミュニティを立ち上げました!【無料】
「大学院生になったけど、将来が不安…」と悩んでいませんか?当コミュニティは、就活情報、自力で稼ぐための情報、その他の有益な知識を共有しあう初の院生特化コミュニティ。「もっと視野を広げたい」と考えている大学院生の方はぜひ参加してみてください。
下記から無料で参加できます。
» 無料の大学院生コミュニティに参加する
※案内のための公式LINEに飛びます。

本記事の内容
本記事の執筆者

うぃる(@willblog13)
この記事を書いているぼくは、2022年3月に大学院を修了し、現在は東京のとある大企業で働いています。
ただ、そんなぼくですが、大学院の選び方は失敗しました。
なぜなら、本質的な大学院の選び方を理解せずに目先の情報のみで進学する大学院を決めてしまったからです。
しかし、大学院を修了した今なら本質的な大学院の選び方を理解できます。
ということで、今回はぼくの失敗談を踏まえつつ、大学院の選び方を解説していきます。
あわせて読みたい
-

【厳選】自己分析ツールのおすすめ7選【登録なし/無料あり】
続きを見る
本質的な大学院の選び方

ここでは、本質的な大学院の選び方を解説していきます。
このあと、「その他の大学院の選び方5選」と題して大学院の選ぶポイントも解説しますが、あまり本質的ではありません。
まずは、この章を理解することから始めてください。
「やりたいこと」から逆算して大学院を選ぶ
結論、本質的な大学院の選び方は「やりたいこと」から逆算して選ぶことです。
「やりたいこと」から逆算して選ぶとは、以下の通り。
- 間違い:大学院を選ぶ→研究できるジャンルを知る→その中から自分の「やりたいこと」を探す
- 正解 :「やりたいこと」を明確にする→「やりたいこと」を学べる研究室を探す→その研究室がある大学院を選ぶ
どうでしょう。後者の方が本質的な大学院の選び方ですよね。
とはいえ、ぼくは前者でした。その頃何も知らなかったので…。
でも、前者の選び方はぼくだけではなく、多くの人がしているはず。
多分この記事を読んでいるあなたもドキッとしたかもしれませんね。
やりたいことがないと進学してから苦労する
では、なぜ「やりたいこと」から逆算して大学院を選ぶのかというと、研究内容が「やりたいこと」でないと進学してから苦労するからです。
人間がたいしてやりたくもないことを2年間続けるのは苦難の技。
やりたいことではないからモチベーションが高まらない→研究が進まない→研究の成果がでない→モチベーションが下がる、というループに陥ってしまいます。
実際、ぼくも修士の2年間はかなりきつかったです。
でも、ぼくは幸運なことに研究していたことに興味が持てたので、なんとか乗り切ることができました。
なので、現在大学院の選び方で悩んでいる人は、ぜひ自分の「やりたいこと」を明確にすることをおすすめします。
ちなみに、やりたいことを見つけるには下記の書籍がおすすめ。
そもそもやりたいことがないなら大学院に行く必要なし
ここからはそもそも論を語ります。
それは「やりたいこと」がないなら大学院に行く必要なくね?ということ。
目的のない中で大学院に通い続けるのは、普通に無駄です。
それだったら、就職したり、大学の段階で休学して「やりたいこと」を探したりしたほうがマシですね。
とはいえ、ぼくのように「もう少し今後の人生を考える時間を作りたい」「もうちょっとモラトリアム期間がほしい」といった大学院に進学する目的があるなら、ぶっちゃけ進学してもいいかと思います。
ここは個々人の気持ち次第ですが、何かしら進学する目的がないと大学院に行く必要ないということは覚えておいてほしいと思います。
-
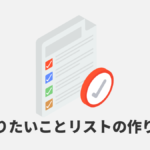
やりたいことリスト100項目の作り方【項目例・テンプレートあり】
続きを見る
その他の大学院の選び方5選

ここからは前段の「本質的な大学院の選び方」を見たうえで、それでも大学院の選び方に悩んでいる人が参考にしてください。
早速解説していきますが、おすすめの大学院の選び方が以下の5つ。
- 大学院の立地
- 学費や奨学金
- 外国人留学生の受け入れ実績
- 大学(院)のブランド
- 修了生の進路
それぞれ解説していきます。
①大学院の立地
まずは、大学院の立地です。
一番最初に書いた理由は、ぼくが一番重視してよかったと思っていることだからです。
研究室に通っていると通学時間って結構ストレスになるんですよね。
しかも、ときには深夜まで研究をするなんてこともあるので、できるだけ家に近い方がいろいろ都合がいいです。
実際、ぼくはチャリで15分くらいのところの大学院に通っていたおかげで、通学によるストレスはほとんどありませんでした。
もちろん、他の要素も合わせて考えたほうがいいですが、立地も一つのポイントとして抑えておくのは重要だと思います。
②学費や奨学金
続いては、学費や奨学金。
大学院進学には当然学費がかかるわけなので、しっかりと見極めないといけません。
例えば、国立・私立というだけでも変わってきます。
- 国立大学院:入学料282,000円、授業料535,800円(標準額より)
- 私立大学院:入学料202,598円、授業料776,040円(449大学の平均値)
引用(国立):平成22年度国立大学の授業料、入学料及び検定料の調査結果について:文部科学省
引用(私立):私立大学等の令和2年度入学者に係る学生納付金等調査結果について:文部科学省
やはり授業料を考えると2年間のトータルは私立大学院の方が上回ります。
その他にも大学ごとに奨学金のあれこれも変わってくるので、きちんと下調べは必要になります。
上記のお金に関することを配慮しつつ、進む大学院を選ぶことが重要です。
③外国人留学生の受け入れ実績
ぼく個人が重要だと思うのが、外国人留学生の受け入れ実績です。
なぜなら、大学院生になると外国人留学生と交流する機会が増え、それが英語力を伸ばすチャンスにつながるからです。
実際ぼくも大学院生時代は留学生のチューターなどを担当し、そこで話せないもどかしさ等を感じて英語学習のやる気を保っていました。
2020年以降はコロナの影響で留学生の受け入れが下がっているらしいですが、きちんとチェックしておくようにしましょう。
-

大学院で求められる英語レベルはどれくらい?【勉強法も紹介】
続きを見る
④大学(院)のブランド
これこそ本質的ではないですが、大学(院)のブランドというのも選ぶポイントになるかなと思います。
理由はシンプルで、まだ日本には学歴至上主義的な考えが残っているからですね。
実際、大企業に入って思いますが、同期も先輩も大抵偏差値の高い大学院出身の人ばかりです・・・。
なので、今後就職をしてよい企業に入りたいというのなら、多少大学院のネームバリューを意識するのは大事かと思います。
⑤修了生の進路
④に続いて、就職に関するポイントですが、修了生の進路実績についても重要な選び方です。
結局は大学院を出たら就職するわけなので、進路実績を確認しておくのは大事。
下記のポイントを確認しながら、進路実績と照らし合わせていくのがおすすめです。
- 将来どんな職に就きたいのか
- 大学院で学んだことをどう活かしていきたいのか
また、進路実績を確認するとともに、どんな仕事・企業があるのかをリサーチすることも重要です。
大学院生の就活に関する詳しい情報は『大学院卒は就職において有利?【学部卒との違いも解説】』にて解説しています。
-
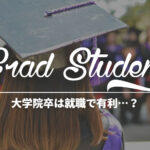
大学院卒は就職において有利?【学部卒との違いも解説】
続きを見る
研究室のおすすめの選び方も紹介

大学院を選ぶ際に重要となるのが、研究室の選び方です。
最初の方でも述べたように「やりたいこと」から逆算していくと大学院を選ぶ前に、研究室選びが先に来ることが多いと思います。
ですが、研究室にも一癖あるので、きちんと選び方を把握しておいたほうがいいです。
ということで、研究室の選び方については、まとめました。それがこちら。
- 研究内容
- 担当教授
- 研究環境
- 忙しさ(ゼミ頻度など)
- 大学院修了後の進路
研究内容
一番重要なところです。最初の「本質的な大学院選び」でも述べたように、自分が興味のある研究内容があるかどうかをしっかりリサーチしましょう。
本当に研究は地道かつ地味な作業が多いので、好きなことでないと病みます笑
また、できるだけ学ぶことや実際にどんな調査をするかなどもリサーチしましょう。
タイトルだけ見たら興味ある研究テーマだったけど、蓋を開けてみたら苦手なプログラミングをするだけだった、という可能性もありえます。
そういった状態にならないためにも、研究室訪問をするなどして情報収集しましょう。
担当教授
続いて、自分が所属しようと思っている担当教授について調べてみましょう。
というのも、賢威のある教授だと、外部との接触ができるからです。
実際、ぼくも教授のつながりで、国交省のお偉いさんから定期的に研究に対する助言をもらったりもしていました。
なので、研究内容とともに担当教授についても詳しくリサーチしておきましょう。
具体的には、以下の項目を調べておくといいです。
- 教授の経歴
- 発表論文
- 所属学会やその役職
基本的には、その教授の名前でググればOKです。そうすれば、大学のHPなどで教授の経歴などを調べられます。
さらに、研究室訪問で直接話しを聞くってのもありですね。
研究環境
研究を進めるうえで、研究環境も大事です。
- 研究室は広いか
- 研究室はきれいか
- 研究室で使用しているPCは新しいか
- どれくらいの人数が研究室にいるか
- 実験環境が整っているか
細かいところですが、意外と重要です。
2年間研究を続けるにはモチベーションも必要。そのモチベーションを保つためにも、研究環境はしっかりリサーチしておきましょう。
忙しさ(ゼミ頻度など)
また、研究室の忙しさも知っておきましょう。特にゼミの頻度とかですね。
というのも、大学院生といえど、プライベートの予定もありますよね。
やっぱり息抜きは必要になるので、365日24時間研究漬けにならないように、気をつけましょう。
大学院の忙しさについては、『「大学院生は忙しい?」→答えはYes【結論:ただ、サボってOK】』で解説しています。
-

「大学院生は忙しい?」→答えはYes【結論:ただ、サボってOK】
続きを見る
大学院修了後の進路
最後に、大学院修了後の進路についても把握しておきましょう。
というのも、実際に進路を見ると、自分が大体どのランクの企業に行けるかが見えてくるからです。
さらに、実績があるということは、その企業に対するノウハウも研究室に溜まっているということ。もしくは、教授にコネがある可能性もあります。
そんな風に就活を有利に進められるので、大学院修了後の進路を調べておきましょう。大体大学院のHPや研究室のHPをググれば出てきます。
また、『研究室選びと就職は関係ある?失敗しないための選び方を紹介』を見れば、就活を意識した研究室の選び方のポイントを学べるとともに、研究室選びと就職活動の関係についても学べるのでぜひご覧ください。
-
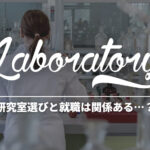
研究室選びと就職は関係ある?失敗しないための選び方を紹介
続きを見る
それでは、また。
あわせて読みたい
-

【無料】大学院生向け就活サイトのおすすめ12選【注意点あり】
続きを見る

